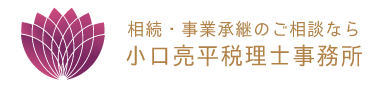教育資金贈与と相続税
目次
教育資金贈与と相続税
あなたのケースではどうなる?インタラクティブ解説
かんたんルール診断
いくつかの質問に答えるだけで、あなたの状況に適用される相続税の「足し戻し」ルールが分かります。
診断結果
制度改正のタイムライン
教育資金贈与制度:祖父母や親から30歳未満の子や孫へ、教育資金として最大1,500万円までを非課税で一括贈与できる制度です。資金は専用口座で管理され、学校の授業料や塾の費用などに使えます。
「足し戻し」とは:贈与した方が亡くなった際に、専用口座に残っている未使用の教育資金(管理残額)を、相続財産に加えて相続税を計算するルールのことです。この制度が単なる相続税対策として使われるのを防ぐ目的があり、税制改正のたびにルールが厳しくなっています。
シナリオA(2018年の贈与):祖父が孫へ1,500万円贈与。2019年3月31日以前の契約なので、足し戻しルールは適用されません。残額に相続税はかからず、節税効果が最大化されました。
シナリオB(2022年の贈与):祖父が社会人の孫へ1,500万円贈与。2021年4月1日以降の契約で、孫は例外条件に該当しないため、残額は全額足し戻されます。さらに孫なので、足し戻された額にかかる相続税は2割加算されます。
シナリオC(2024年の贈与、富裕層):相続財産7億円の祖父が大学生の孫へ1,500万円贈与。孫は在学中ですが、祖父の相続財産が5億円を超えているため例外規定は適用されません。残額は全額足し戻され、かつ2割加算の対象となります。
今日の制度の有効性:現在の制度は、節税目的よりも「子や孫の教育資金を確実に確保する」という資金管理の側面が強くなっています。相続財産が5億円以下で、将来の相続税リスクを受け入れられる方が主な対象者です。
代替策1:都度贈与:学費などが必要になるたびに、その都度必要な額を支払う方法。扶養義務の範囲内とみなされ、常に非課税です。シンプルですが、事前の資金確保はできません。
代替策2:改正後の相続時精算課税制度:2024年から年間110万円の基礎控除が新設されました。この枠内の贈与は申告不要・非課税で、相続時の足し戻しもありません。教育資金贈与より柔軟性が高く、有力な選択肢となっています。